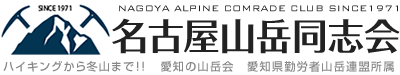【メンバー】
CL:トモちゃん、SL:きんちゃん、はっちー、りゅう、youichi、はっしー、アジータ、mahomaho、ホーリ
ー(記)
【行程】
7:50八風キャンプ場-9:20北山-10:07岩が峰-10:44釈迦ヶ岳-12:00仙香山-12:19八風峠-13:46八風キャンプ場
シロヤシオ観察の山行の案内が来た。毎年4月にアカヤシオの観察のため鈴鹿に行っているが、シロヤシオは久しく観ていない。3年程前に三重県中部松阪奥地の三嶺山のシロヤシオにトライをしたが、花期が短いこともありタイミングが悪く観察できなかった。2024年になって仕事や別の趣味で多忙だったこともあり、久しく山行にもいっていない。6月に会のイベントの清掃山行が御在所岳であることだし、久しぶりに脚を鍛えるのも兼ね、このシロヤシオ山行に参加することとした。
8時に八風キャンプ場とのことなので、6時45分に出発すれば間に合う。しかし、当日の朝かなりどんよりしており午後から雨との予報だ。とはいえ中止の連絡もないためとりあえず集合場所にむけて出発した。7時50分に八風キャンプ場の駐車場到着。思ったより車がなく、しかもメンバーはすでに出発の準備をして待っている。到着するやいなや、天気が悪くなるからすぐ出発すると言われ、急ぎで靴を履きザックを出す。この時、コンビニで購入したごはんやおやつを入れ忘れてしまったことに気づかず出発。性急なのは良くないことに後々気づくことに。
今回の釈迦ヶ岳の八風キャンプ場からのルートは登りが岩が峰尾根のコースである。鈴鹿山系は基本的に三重県側が急傾斜で滋賀県側が緩傾斜の傾動地塊の山域であるため、三重県側のこのコースも例に漏れずかなり急である。2年に一度は来ているが、こんなに急だったのかと思ってしまう。しばらく登っていくと淵がほんのり赤い葉5枚セットの中木が登山道脇に観察されるようになる。これがシロヤシオ、別名ゴヨウツツジである。少し先の4月に咲くアカヤシオの対としてのシロヤシオの名前なのだろうが、この標高帯ではまだ白い花は観察されない、すでに落花しているのか、あるいはまだ開花していないのかもしれない。山脈の稜線近くになり、一本の木に2,3個の花が観察される木が散見されるようになる。間違いなく開花する標高帯なのだろうが、あまりに花が少ない。シロヤシオは隔年で花の量が変わるという話もあるので、今年はいわゆる外れ年なのかもしれない。
そうこうしているうちに岩が峰尾根の稜線に着く。ここから釈迦ヶ岳は20分程度なので、天候が微妙ながらも山頂には到達しておきたく、山頂まで移動してメンバーで記念撮影をした。しかし、ここから霧雲が三重県側の斜面をはって上昇してきて、視界がかなり悪くなってきた。しかし、雨ではないので特に問題はなく、むしろ涼しくて快適であり、鈴鹿に居ながらにしてアルペン的な風景になってきたため、逆にこの風景を楽しめていた。
この釈迦ヶ岳から三池岳へはあまり標高差のない稜線が続く。本来三重県側は伊勢平野や伊勢湾が広がる良い風景の場所だが、今日は雲と霧で何も見えない。登山道脇には時折芝生やトピアリーの様な柘植の木が見られ、日本庭園さながらの場所もあった。鈴鹿の山では御池岳やイブネの山頂付近ように時折このような場所が存在するのが不思議である。急ぎルートを北上する中、昼食をとることとなった。が、車に全て忘れてきた私は、食べるものがない。メンバーの余分のパンやお菓子を恵んでもらいなんとか今回は耐えることができた。
さらに北上してやっと八風峠に到着。ここは伊勢と近江をつなぐ昔の街道の1つで、滋賀県側の集落を拠点とした木地師(木工食器などを作成する職人)が食器を背負って伊勢側運んだ道である。昔は朽ちた鳥居があり荒涼な雰囲気の峠だったが、今では古い鳥居は撤去され、朱色の小さめのしっかりした鳥居と神様を祭った洞が設置されている。
八風峠から三池岳経由で尾根筋を登る計画ではあったが、この後の天候悪化が予想されるため、時間短縮と樹林帯の中の方が風雨をしのげることから、谷筋の八風街道で降りることと判断された。この道を歩くのは初めてである。大昔の街道のため、九十九折りで距離は長いが緩傾斜の道がつづき、要所にお地蔵さんや碑がみられる。やはり街道といった面持ちであり、鈴鹿の山にも歴史があることから、それが垣間見られるのは結構楽しい。しかし、このルートは長い。なかなかつかない。久しく山行に行っていなかったため、太ももの筋肉が悲鳴を上げ始めついには両太ももとも攣りそうになり、歩き方を微妙に変え、塩飴や芍薬甘草湯等を飲むなどあらゆる手を尽くして脚の維持に努めた。その甲斐もありなんとか出発地点の駐車場に到着した。結局は殆ど雨には降られなかった。次回の山行の約束等をして、めいめい解散となる。いつものように鈴鹿の山麓の巡検街道を北上しつつ散策して、帰路に就いた。今回も一風変わった鈴鹿中部の山を体験することができ、しばらく遠ざかっていた登山意欲も復活しつつあるのがわかった。今回も、企画してくれたリーダーには感謝したい。ありがとうございました。